MBTIで読み解く「バイヤーの適性」とチーム力強化のヒント
はじめに
「調達の仕事に向いている人って、どんな性格だろう?」
そんな問いは、経営層や管理職の方なら一度は考えたことがあるはずです。
購買・調達は会社の利益に直結する重要な業務ですが、必ずしも“花形”ではなく、配属された若手がモチベーションを保てずに離職…というケースも少なくありません。
ここで参考になるのが MBTI(Myers-Briggs Type Indicator) という性格タイプ診断です。
全てを鵜呑みにする必要はありませんが、 「人材をどう活かすか」 を考える上でひとつの有効な視点になります。
MBTIとは?
MBTIは、人の思考や行動の傾向を以下の4軸で分類し、16タイプに整理するフレームワークです。
- 外向(E)/内向(I)
- 感覚(S)/直感(N)
- 思考(T)/感情(F)
- 判断(J)/知覚(P)
若手層では「就活の自己分析」で広く使われており、企業の研修にも導入されるケースが増えています。
ただし注意すべきは、MBTIはあくまで「傾向を知る道具」であって、
人材を型にはめるものではないという点です。
調達に求められる力とMBTIタイプの対応
調達・購買業務では以下のような要素が求められます。
- 論理的・分析的思考力:市場価格分析、コスト削減策立案
- 計画性・組織力:納期管理、在庫調整、サプライチェーン最適化
- 交渉力・コミュニケーション能力:価格・条件交渉、社内部署との調整
- 責任感・実務遂行力:契約・品質確認、会社利益を左右する判断
ここにMBTIを重ね合わせると、人材の「強みの出し方」が見えてきます。
1. ENTJ・ESTJ(指揮官・管理者)
「交渉の鬼」。
数字を駆使した論理的な交渉でサプライヤーを納得させ、社内の意思決定をグイグイ前に進める力を持ちます。
経営層からすると「原価低減プロジェクトの旗振り役」に最適です。
ただし強引さが出すぎると関係を損なうリスクもあるため、チームにF型(感情型)を組み合わせるとバランスが取れます。
2. INFJ・ENFP(提唱者・運動家)
「人の気持ちを読む翻訳者」。
設計や生産部門の“本音”を引き出し、サプライヤーにわかりやすく伝える力に長けています。
新規サプライヤー開拓や海外調達で「文化や考え方の違い」をつなぐ役割に適しています。
経営層視点では「現場とサプライヤーの架け橋」になれる存在です。
3. ISTJ・INTP(管理者・論理学者)
「データと仕組みの守護者」。
在庫の数字や購買データを読み解き、どこに無駄があるか瞬時に把握します。
ERPやBIツールを駆使し、業務フロー改善や標準化を進める人材として頼りになります。
短期的な交渉より、中長期のコスト構造改善に強みを発揮します。
4. ESFP・ENFJ(エンターテイナー・教師)
「関係構築のムードメーカー」。
雑談の一言が交渉突破口になることも。サプライヤーとの信頼を厚くし、トラブル時の“助け舟”を引き出せるのはこのタイプです。
特に中小企業においては「人間関係の調達力」が業績を左右するケースも多く、彼らの強みは軽視できません。
MBTIをどう活かすか(経営層へのヒント)
- 採用・配置に活かす
「交渉型」「分析型」「調整型」など、調達業務の中で役割を振り分ける参考に。 - チームビルディングに活かす
ENTJの推進力 × INFJの調整力 × ISTJの管理力 × ENFPの関係構築力。
多様性を組み合わせることで“調達部門の地位”は自然と向上します。 - 育成に活かす
タイプごとに苦手分野を補う教育を設計。
例:データが苦手なENFPには在庫分析の基礎研修を、強引になりがちなESTJには関係構築のロールプレイ研修を。
注意点と偏見防止
- MBTIは診断結果が絶対ではありません。
- 人材の価値を「型」で判断するのではなく、強みをどう生かすかに目を向けるべきです。
- 経営層が陥りやすい誤解は「このタイプは不向きだから採らない」。
→ むしろ 不向きに見えるタイプがチームを補完する ことが多々あります。
まとめ
調達の現場は「数字」と「人間関係」の両立が常に求められます。
MBTIをヒントに、それぞれの強みを活かすことで、
伝書鳩ではなく「攻めの調達」へと進化させることが可能です。
RE:GENでは、調達部門の人材育成や組織力強化の支援を行っています。
性格診断を鵜呑みにするのではなく、一人ひとりが光る場をどう作るか。
その実践を、ぜひご一緒できればと思います。
「ちょっと話を聞いてみたい」でも大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
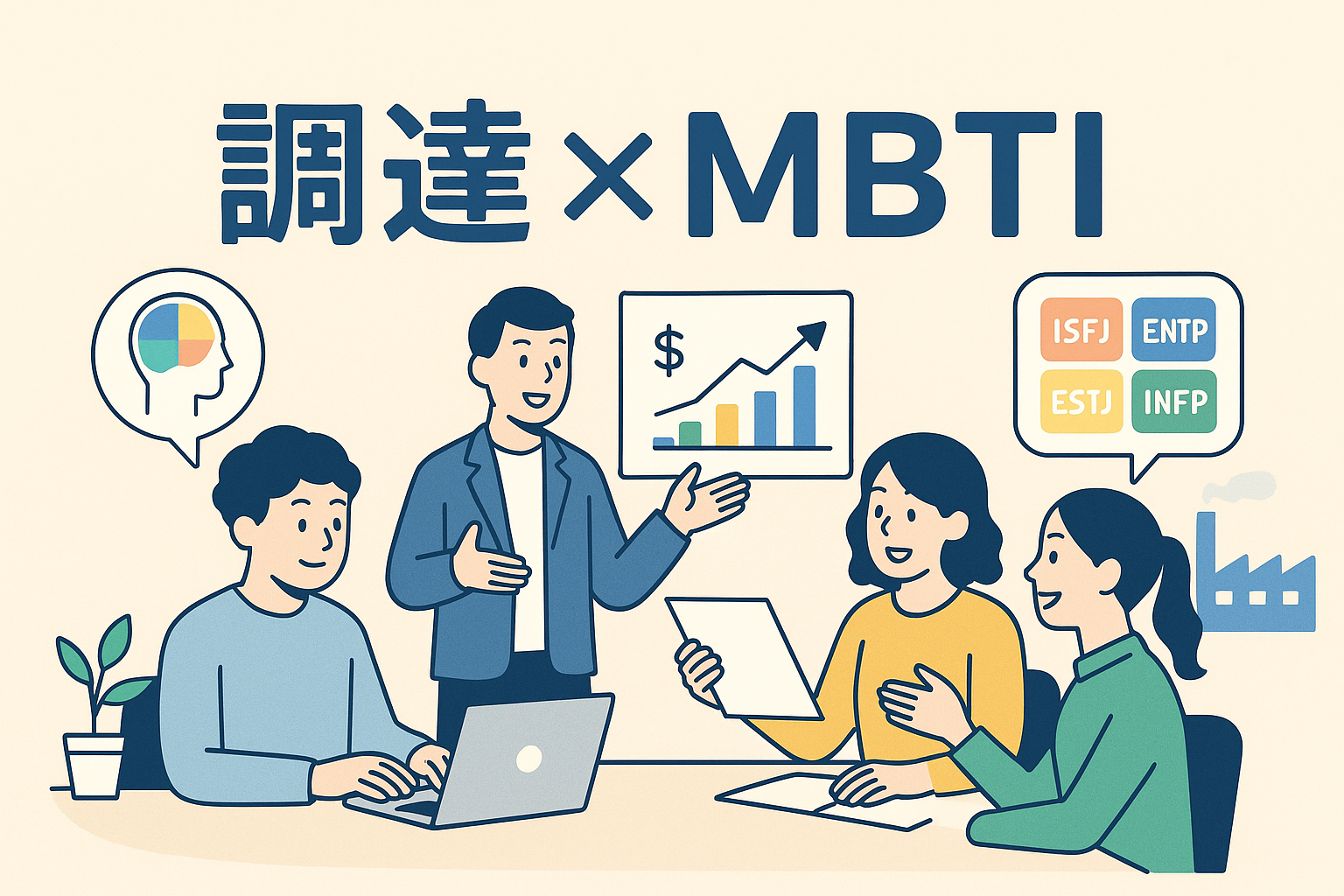
コメント