1. 営業や技術は多いのに、なぜ「調達出身」の経営者は、これほどまでに少ないのか?
これまで数多くの経営者の方々と接してきましたが、その経歴を伺うと、大半が営業や技術、あるいは企画部門の出身です。「調達畑一筋で経営トップになった」という方には、残念ながらほとんど出会ったことがありません。日本企業の経営層において、調達出身者は極めて珍しい存在です。
なぜ、会社の利益に直結する「調達」という重要な機能から、未来を牽引する経営人材が育ちにくいのでしょうか?この問いの裏には、日本企業が長年抱えてきた、「見えないムダ」を放置し続けてきた構造的な課題が隠されています。
2. 調達が“軽視”されてきた構造的な背景と、その代償
調達という職能が経営層まで至らない背景には、いくつかの根深い要因があります。
• 「売上」と「利益」の評価軸の歪み:
営業は「売上を上げる」、技術は「新製品を生む」と、その貢献が直接的で「華やか」に見えます。一方、調達は「コストを下げる」「品質を守る」と、その貢献が「守り」や「裏方」と捉えられがちです。これにより、調達がどれだけ利益に貢献しても、その「見え方」が経営層に正しく評価されてきませんでした。
• 「価格交渉係」という固定観念:
調達の仕事が「安く買い叩くこと」だけだと誤解され、「サプライヤーとの関係を悪化させる存在」と見られることも少なくありません。本来の調達は、サプライヤーと長期的な信頼関係を築きながら、最適な価値を引き出す「共創」のプロであるべきなのに、その本質が見過ごされてきました。
• 「経営視点」が育ちにくいキャリアパス:
調達部門の業務が、上司の承認を得るための単なる「申請業務」や「価格交渉」に終始してしまうと、会社全体の利益構造やリスク、事業戦略といった「経営視点」を養う機会が限られてしまいます。経営幹部への意図的なキャリアパスが整備されてこなかったことも、大きな要因です。
このような要因が重なり、調達は「会社に欠かせない機能」でありながら、その真の価値が経営層まで届かず、結果として**「会社全体の利益を最大化する視点」が経営に十分に反映されない**という大きな代償を払ってきました。
3. 「原価」を握る調達こそ、経営の「攻め」を支える根幹である
しかし、数字が示す調達の価値は揺るぎません。
• 「原価1%削減」の破壊力:
売上を1%伸ばすには、多大な労力と広告宣伝費がかかります。しかし、原価を1%削減するだけで、営業利益は数%〜数十%も改善することがあります(利益率が低いほどその効果は絶大です)。これは、売上を増やすことと同じ、あるいはそれ以上の「利益創造」に匹敵します。
• 企業競争力そのもの:
他社より高品質なものを安く、安定して調達できる力は、製品の競争力を直接左右します。原材料高騰や供給不安が続く現代において、優れた調達力は、企業を存続させるための生命線です。
• 未来のリスク管理と持続可能性:
サプライチェーンのリスク、環境問題への対応、人権問題への配慮(サステナビリティ)など、現代の経営課題の多くは「サプライヤーとの関係」に起因します。これらを最前線で管理し、会社の未来の成長をリスクから守っているのは、まさに調達部門なのです。
つまり、調達は単なる「守りのコスト削減」ではありません。会社の利益構造に直接影響を与え、未来のリスクを見据え、**経営の成長と安定を支える「攻めの武器」**そのものです。
4. 松下幸之助の「社員稼業」に学ぶ、調達と経営の本質
ここで、私がRE:GENの信念とする松下幸之助の言葉を引用させてください。
• 「利は元にあり」:利益は、単なる安売りで生まれるものではない。お客様、取引先、そして社会との共存共栄の中にこそ、本当の利益が生まれる。
• 「社員稼業」:社員一人ひとりが、自分の持ち場を「自分の商売」として捉え、会社の経営を背負う意識と責任、そして誇りを持つべきだ。
この二つの思想は、まさに調達職能の本質を突いています。
調達担当者は、サプライヤーとの信頼関係を築きながら「共存共栄」を追求し、会社全体にとって最も良い選択(全体最適)を考えなければなりません。
そして、「自分の稼業」として数字を深く追い、利益構造を改善し、経営全体を背負う覚悟を持つ。
これらは、まさに経営者に求められる視点そのものです。調達担当者が「社員稼業」を実践するとき、その視点はすでに経営者レベルに達していると言えるでしょう。
5. これからの日本企業には「調達の視点を持つ経営者」が不可欠である
日本企業はこれまで、売上を作る営業や製品を作る技術を中心に経営を回してきました。これは経済成長期には有効でしたが、グローバル化、サプライチェーンの複雑化、SDGsや環境対応といった新たな経営課題が山積する現代においては、もはや十分ではありません。
• 営業出身経営者の限界: 売上増には長けるが、利益率やコスト構造、サプライチェーン全体のリスクへの視点が不足しがち。
• 技術出身経営者の限界: 新製品開発には強みを発揮するが、市場競争力のある価格設定や、安定した部材調達戦略への視点が手薄になることも。
一方で、世界に目を向ければ、調達のプロが経営トップに立ち、企業を大きく成長させている事例があります。その筆頭が、Appleのティム・クックCEOです。彼はCOO(最高執行責任者)時代に、卓越したサプライチェーンマネジメントと調達戦略で、Appleの生産効率と利益率を劇的に改善させました。彼の辣腕がなければ、iPhoneの世界的成功はなかったとも言われます。調達という「守り」に見える機能が、いかに「攻め」の経営を支え、企業の成長エンジンになり得るかを、彼は体現しているのです。
これからの日本企業には、**「原価から利益を創り出し、サプライチェーン全体のリスクを管理し、持続可能な経営を実現する」**という、調達が持つ本質的な視点を経営の中心に据えられるリーダーが不可欠です。調達出身の経営者が増えることは、単なるキャリアパスの多様化に留まらず、日本企業全体の体質を根本から強くする、未来に向けた戦略的投資なのです。
6. RE:GENとしての覚悟:調達を「経営の武器」へ、そして次世代のリーダーへ
私たちRE:GEN(利元)は、「利は元にあり」の精神を社名に込め、調達が持つ本来の力を信じています。
調達は、単なる価格交渉部署ではありません。それは、会社の利益を最大化し、未来のリスクから守り、持続的な成長を支える「経営の最強の武器」です。そして、その武器を使いこなせる調達人材こそが、次世代の経営リーダーになり得る。
調達出身の経営者はまだ少数派かもしれません。しかし、この流れは確実に変わりつつあります。RE:GENは、その変化を加速させるために、調達部門の強化を通じて経営者視点を持つ調達人材の育成に貢献し、日本企業の未来を共に創っていく覚悟です。
「ちょっと話を聞いてみたい」でも大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
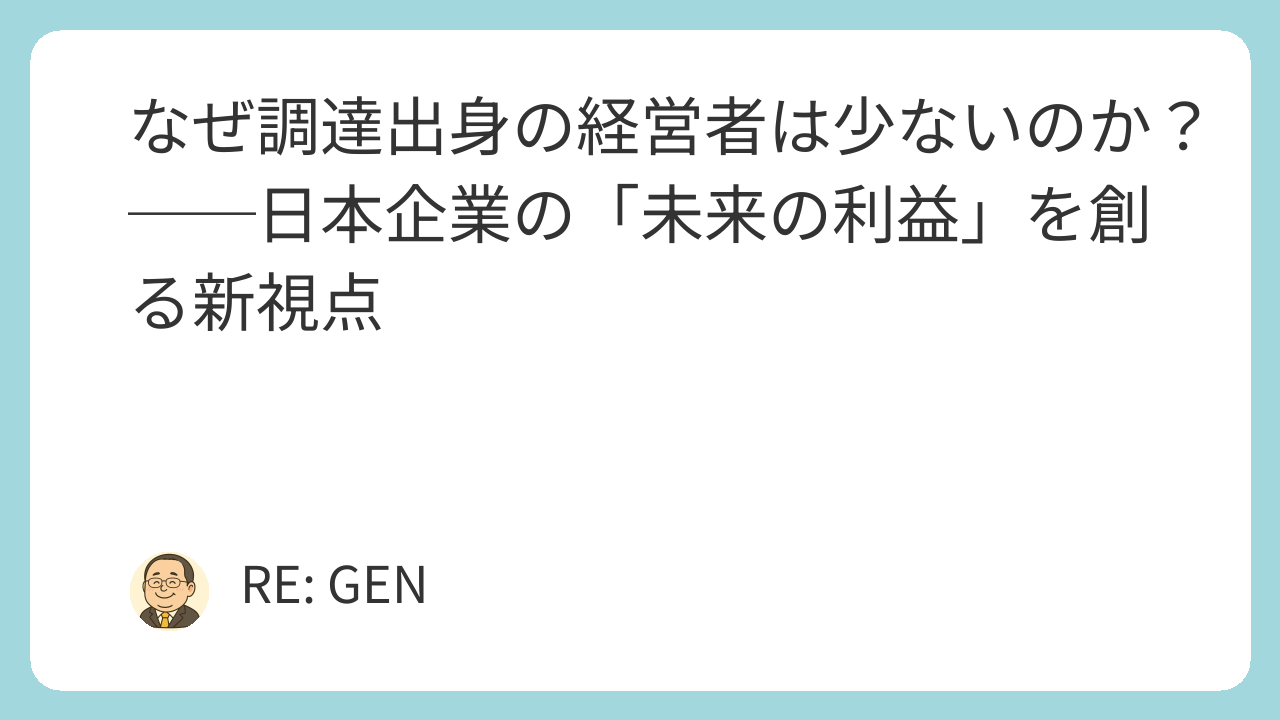
コメント