多くの経営者の共通悩み
「もうコスト削減はやり尽くした」
そんな声を、経営者や管理者の方からよく耳にします。
人件費や光熱費などの固定費を抑える取り組みは確かに効果があります。しかし限界も見えやすく、社員の負担増やサービス低下につながるケースも少なくありません。
ところが、会社の支出の大半を占める「調達費用」は、まだまだ改善余地がある分野です。にもかかわらず、多くの企業では調達が軽視されがち。ここにこそ「隠れた利益源泉」が眠っています。
コスト削減の限界
- 単純に“削る”だけのコストカットは、持続しない
- 無理な価格交渉はサプライヤーとの信頼関係を壊す
- 品質低下や納期遅延のリスクが高まる
短期的には数字が改善しても、長期的には企業体質を弱めてしまうのが現実です。
調達を見直すと開ける可能性
調達を見直すことで、単なるコストダウン以上の成果が期待できます。
- サプライヤーの選定を変える
新規開拓や相見積もりで条件改善の余地は大きい。 - プロセスを整える
標準化された相見積もり、適正な在庫設計。業務が効率化し“当たり前”の質が向上。 - 情報を開く
コスト構造を理解することで、数字に基づいた前向きな議論が可能に。
結果として、品質向上、納期安定、新技術導入など「成長を支える調達」へと進化します。
実例が示す「隠れた利益」
- 競争環境のなかった購入先を見直した結果
月226万円のコスト削減を達成。 - 在庫の考え方を見直した結果
キャッシュフローが改善し、新規投資に回せる余力が生まれた。
調達は、会社の未来を支える“利益の起点”になり得ます。
中小企業が取り組める第一歩
- 相見積もりを一度とってみる
- 滞留在庫を棚卸して把握する
- 小さな改善提案を仕入先に伝えてみる
大切なのは「小さな一歩」。この積み重ねが調達力を磨く原点です。
調達の“地位向上”が企業を強くする
ここからが最も重要な視点です。
調達は「値引き交渉の現場部門」ではなく、経営に直結する戦略部門であることを、経営者がはっきりと位置づける必要があります。
なぜなら、調達は会社のお金が最初に動き出す起点だからです。
ここを経営戦略として捉えれば、調達は「面倒を持ち込む部署」ではなく「利益を設計する部署」として社内の認識が変わります。
例えば――
- 新規サプライヤーを口座開設する際、価格だけでなく品質保証体制やリスク管理のチェックが必須になる
- 得意先への4M変更届など、調達が担う書類対応は「形だけ」ではなく取引継続を守る盾となる
- 社内の設計や生産と協力して改善提案を進める姿勢は、会社全体の信頼を底上げする
経営者が「調達を戦略的に位置づける」と宣言した瞬間から、調達は“社内の負担”から“企業の利益を生む仕組み”へと生まれ変わります。
調達という「隠れた武器」
コスト削減の限界を突破する答えは、調達の中にあります。
- 削るだけでなく、品質・納期・技術を引き上げる力
- 社内外の信頼をつなぐ調整役としての力
- 経営戦略を支える“隠れた武器”としての力
調達の地位を上げ、経営者自らがその価値を位置づけることで、
会社の未来は確実に変わっていきます。
RE:GENがお手伝いしますので
「ちょっと話を聞いてみたい」でも大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
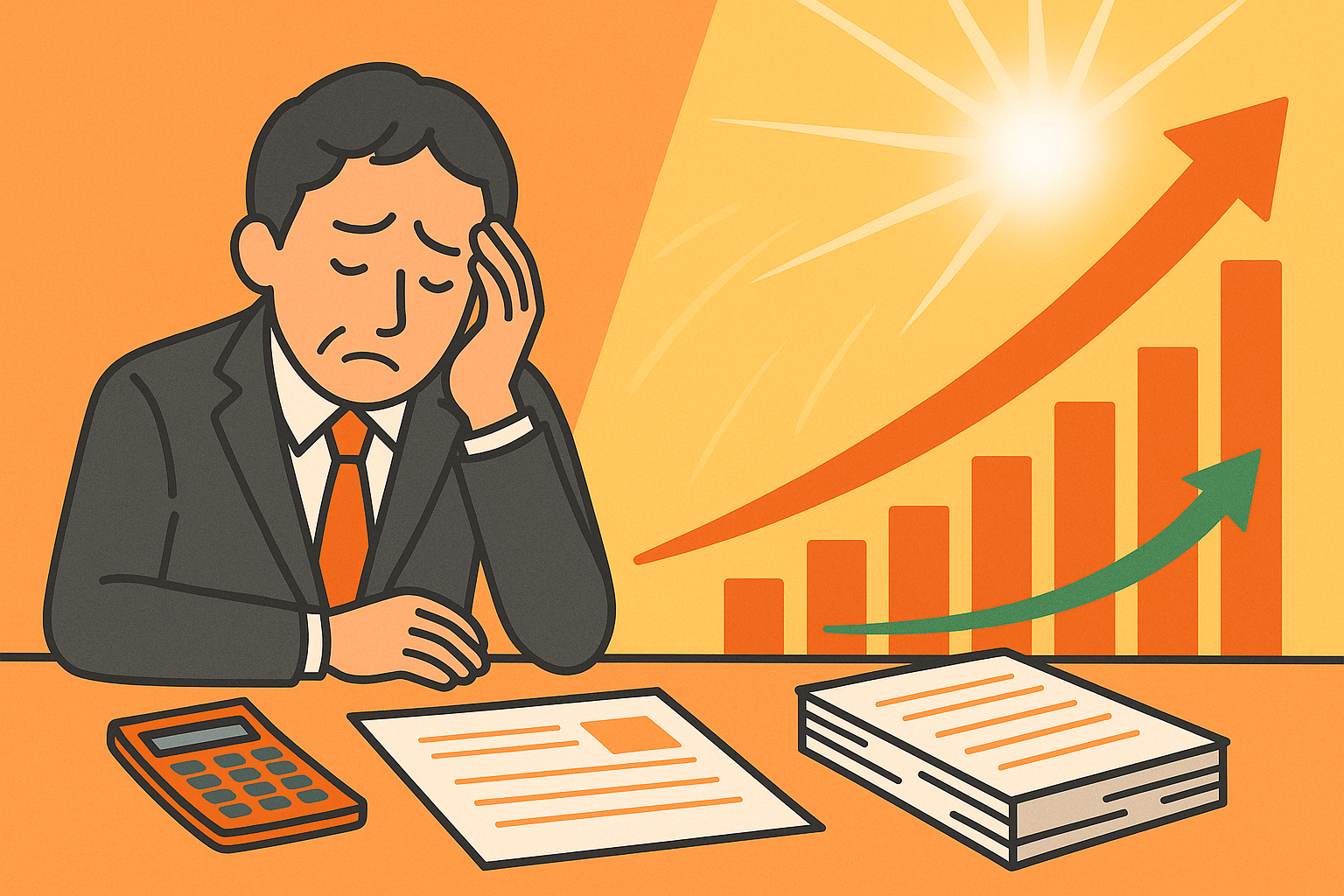
コメント