不良を出さない会社より、不良で強くなる会社
調達の現場で何百という工場を見てきたが、「不良ゼロ」を掲げている会社ほど、どこか危うさを感じることがある。
なぜなら、「不良を報告しづらい空気」を生み出してしまうからだ。
トラブルが起きたときに重要なのは、ゼロの記録ではない。
ゼロに戻すスピードと、二度と起こさないための学習能力である。
不良のない会社ではなく、不良から立ち直り、強くなれる会社こそが、本当の信頼を勝ち取る。
それは「トラブルの回避力」ではなく、「トラブルを成長の糧に変える力」だ。
不良対応こそ、最高の“営業活動”である
不具合が起きたとき、現場から駆けつける品質保証担当者は、しばしば「謝り役」や「後処理班」として扱われる。
しかし、私はいつもこう伝えてきた。
「あなたは、その瞬間の会社の姿勢を体現する“営業マン”なんですよ。」
最初はきょとんとされるが、これは本気の言葉である。
不良対応の場こそ、会社の誠実さを最も分かりやすく伝えられる“最高の営業機会”なのだ。
報告書よりも大切なのは、態度とスピードである。
どれだけ誠実に、どれだけ早く、どれだけ現場を理解して動けるか――その一瞬に、相手の信頼度が決まる。
実際、ある中堅サプライヤーの品質担当者は、納入不良を起こした翌日に暫定対策を提示し、翌週には恒久対策まで整えて持参した。
その姿勢に、調達側は「この会社とならリスクを共にできる」と確信した。結果、取引はむしろ拡大した。
不良は失点ではない。信頼を積み上げ直すためのチャンスである。
【品質担当者へ:これが最高の営業活動だ】
- 謝罪より「事実と暫定策」
感情論より先に、事実の共有と顧客ラインを止めないための具体的行動を提示する。 - 責任追及より「再発防止システム」
再発防止策を見せることで、その会社の技術力と管理体制をアピールできる。 - 不良は失点ではない。
信頼を積み上げ直す最高のチャンスである。
品質対応できないバイヤーが招く「経営リスクの増大」
近年、品質トラブルに自ら関与できないバイヤーが増えている。
「品質は品質部門に任せる」という考え方が広まりつつあるが、これは深刻な問題である。
品質不良とは、単なる技術的な問題ではない。
コスト・納期・信頼関係――すべてに直結する経営リスクそのものである。
バイヤーが品質対応を他部門任せにすると、対応は“社内都合”に偏る。
サプライヤーの立場や再発防止コストを理解しないまま進めれば、対応の遅れが納期遅延の長期化や数億円規模の機会損失に繋がり、
最終的には価格交渉や原価構造の歪みとして跳ね返ってくる。
調達は、品質部門と現場の間に立つ“翻訳者”であるべきだ。
現場の事情と会社の事情を両方理解し、再発防止とコスト影響をバランスさせる。
そこにこそ、「経営の言葉で品質を語る力」が求められている。
不良対応は、企業文化を映す鏡
トラブルの場面ほど、その会社の本性が出る。
A社は、言い訳を並べ、責任を曖昧にしようとした。
B社は、「まず事実を共有させてください」と一言添え、原因と再発防止を丁寧に説明した。
後者には、信頼を取り戻すための覚悟と、技術者としての誇りがあった。
不良対応とは、「どちらが正しいか」ではなく、「どちらが誠実か」を示す場である。
その姿勢が、次の発注、そして長期的なパートナーシップを決定づける。
RE:GENの視点──品質は“守り”ではなく“戦略武器”である
RE:GENは、調達を「コスト削減の手段」ではなく、「経営を強くする戦略武器」として支援している。
品質保証も同じだ。
それはトラブルを防ぐための守りの部署ではなく、
信頼を取り戻す最前線であり、企業の「信頼資産」を積み上げる最強の営業部隊である。
不良を出さないことよりも、出たときにどう動くか。
そして、その対応を全社的な学びとしてどう活かし、サプライヤーとの関係をどう強化するか。
RE:GENは、調達の視点から品質問題発生時のコミュニケーションフロー構築や、
サプライヤーの品質対応力評価スキーム導入を支援し、品質をコストだけでなく、
経営の言葉で語れる“戦略武器”に変えるお手伝いをしている。
品質とは、誠実さの表現である。
不良対応こそ、企業の信頼資産を積み上げる最前線なのだ。
📌 まとめ
- 不良ゼロを目指すより、「不良から立ち直れる会社」が強い。
- 品質保証は、謝る部署ではなく“信頼を売る営業部隊”である。
- バイヤーは、品質部門と現場の“翻訳者”であり、経営の言葉で品質を語る存在である。
- 品質対応の姿勢こそが、企業文化と調達力を映す鏡になる。
👉 関連コラム
「ちょっと話を聞いてみたい」でも大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
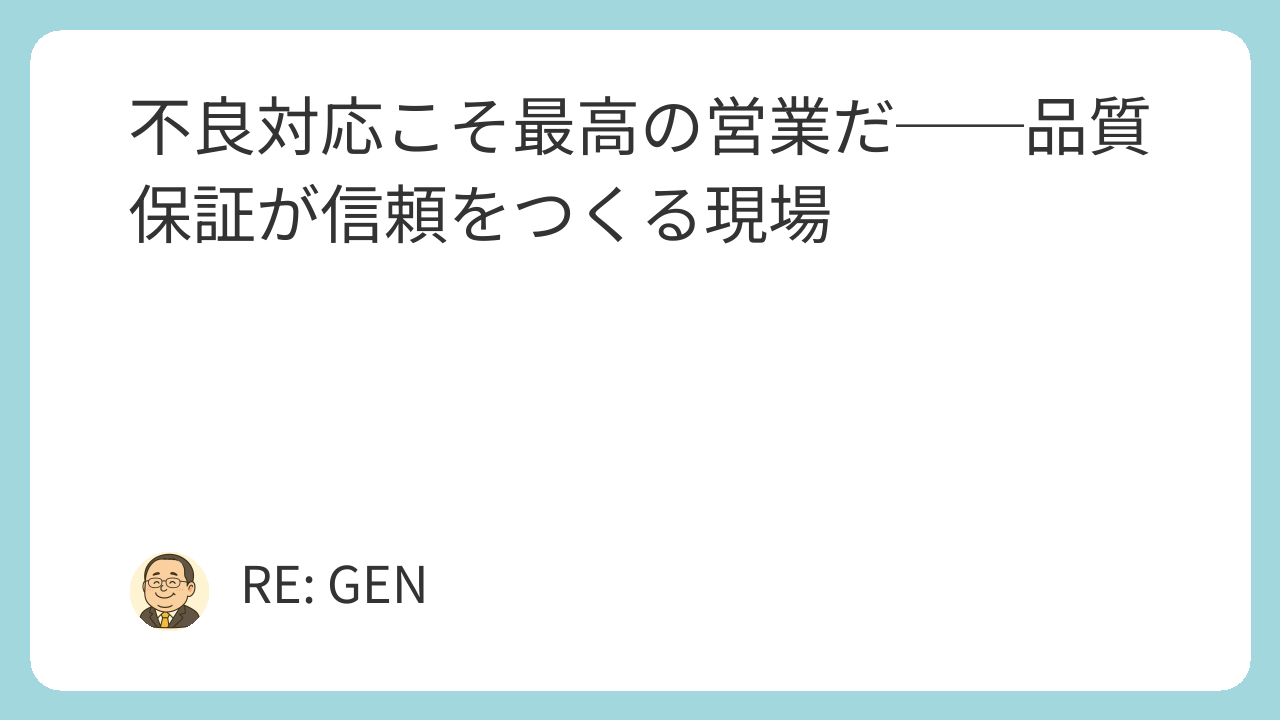
コメント