アルマイトとは?
アルマイトは、アルミニウムを「陽極酸化処理」することで表面に人工的な酸化皮膜を作る処理です。
わかりやすく言えば、アルミの表面に透明で頑丈な“鎧”をまとわせる技術。
この皮膜は肉眼では透明に近いですが、染色することで黒や赤、青といった鮮やかな色合いを出すこともできます。そのため、見た目のデザイン性と機能性を両立できる処理として、多くの製品に使われています。
アルマイトの主な特徴
- 耐食性が高まる:裸のアルミは意外と弱く、すぐに腐食します。アルマイトで酸化皮膜を作ることで、雨や汗に強くなります。
- 耐摩耗性が増す:皮膜は硬く、日常的な擦れや引っかきに強い。
- 絶縁性がある:電気を通さない特性も。電気機器の部材にも利用されます。
- 装飾性:カラーアルマイトによって美しい仕上がりが可能。
調達現場では、「見た目重視なのか」「機能重視なのか」で、どのグレードのアルマイトを選ぶか変わってきます。
よく比較される表面処理との違い
塗装との違い
- 塗装は表面に膜を“乗せる”処理。
- アルマイトは表面そのものを“変質”させて皮膜を作る処理。
結果として、塗装は剥がれる可能性がありますが、アルマイトはアルミと一体化しているため剥がれにくいのが特徴です。
めっきとの違い
- めっきは別の金属をコーティングする手法。
- 耐食性・装飾性の向上は共通しますが、アルマイトはアルミ専用の方法です。
調達現場でのアルマイトあるある
- 「とりあえずアルマイトで」問題
図面に指定がなくても「見栄え良くしたいからアルマイトしておいて」と依頼されることがあります。
ただし、実際にはコスト増につながり、不要な場合も多い。 - 仕様のあいまいさ
「アルマイト処理」とだけ書かれていても、膜厚や色を指定しないとサプライヤーごとに仕上がりが違ってしまいます。 - サプライヤー選定の難しさ
アルマイト処理業者は地域によって数が限られるため、輸送費やリードタイムに影響が出やすい。
ここで「どの業者なら短納期に対応できるか」がバイヤーの腕の見せ所です。
発注時の注意ポイント(調達担当者の視点)
アルマイトを依頼するときに必ず押さえたいのは次の点です:
- 膜厚の指定
標準は 5〜20μm 程度。装飾なら 5〜10μm、防食なら 10〜20μm が目安。
無駄に厚くするとコストアップになるので注意。 - 色・外観
黒・銀・赤・青などのカラー指定が必要。設計者と意思疎通を忘れずに。 - 用途と環境
屋外用途か室内用途かで、必要な耐食性能が変わる。 - リードタイムの確認
アルマイトは外注になるケースが多く、「処理だけで数日追加」になることがあります。スケジュールに必ず組み込んでおきましょう。
まとめ:調達判断の武器としてのアルマイト知識
アルマイトは単なる「見栄えを良くする処理」ではありません。
耐食性や耐摩耗性を付与し、製品寿命を延ばすと同時に、コストや納期にも大きな影響を与えます。
調達担当者としては、**「本当にアルマイトが必要か?」「仕様は適切か?」**を判断することが利益に直結します。
RE:GENでは、大手メーカーでの実践知をベースに、中小企業でもすぐ活かせる調達知識を発信しています。
表面処理ひとつの理解が、コストや品質、そして取引先との関係づくりにまで影響します。
ぜひ日々の調達判断に役立ててください
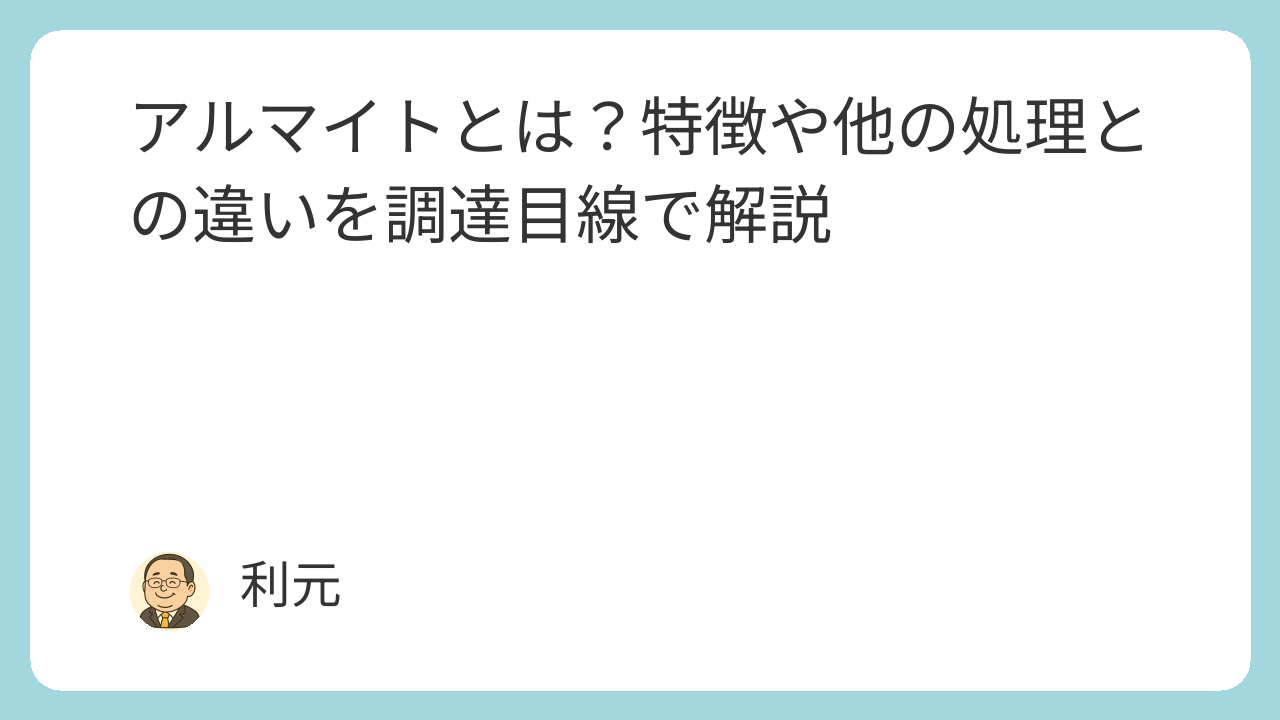
コメント