値上げ交渉は本当に通る?
公取委の「価格転嫁ガイドライン」とバイヤー目線での注意点
~中小企業が知っておきたい調達の常識~
値上げ交渉に公取委が関わる理由
中小企業が仕入先として大手メーカーに部品やサービスを供給するケースは、日本の産業でよくあります。
しかし「原材料費が上がったから価格を上げたい」と思っても、買い手が強すぎると交渉すらできないことがあります。
そこで公正取引委員会(公取委)は「正当な理由があれば価格を上げても良い」というルールをガイドライン化し、健全な取引を守ろうとしています。
価格転嫁ガイドラインのポイント
公取委の「価格転嫁円滑化ガイドライン」では次のように明記されています。
- 原材料費や人件費の高騰は値上げの正当な理由になる
- 買い手が一律に値上げを拒否するのはNG
- 「買いたたき」と見なされれば独禁法や下請法違反の可能性
つまり、サプライヤーの声を「聞かない」態度そのものがリスクになり得るのです。
メーカー側に求められる確認義務と証跡管理
意外に知られていませんが、メーカーには「仕入先に値上げが必要かどうか確認すること」が推奨されています。
さらに、そのやりとりを 証跡として残すこと まで求められています。
「値上げを持ちかけるのは気が引ける」と感じるサプライヤーも多いですが、実際にはメーカー側が確認しなければならないのです。
バイヤーが値上げを認めるケースとは?
調達経験から言うと、バイヤーも「全て断る」ことはできません。
なぜなら 「聞く耳を持たないだけで法令違反」 と見なされる可能性があるからです。
そのため最近では、
- 形式的にでも「一度は値上げ要望を聞く」
- 交渉記録を残す
という動きが広がっています。
ただし一方で、便乗的な「一律◯%アップ」は逆に不信感を持たれます。
私がバイヤーなら「値上げは認める代わりに、別のコストダウンを一緒に考えてください」と返すでしょう。
(半分脅し、半分笑い話ですが…これが現場感です)
サプライヤーが値上げ交渉で注意すべき点
- 「一律で5%アップ」では説得力が弱い
- 原材料費・物流費などの内訳を整理して提示する
- 数字やグラフなど客観的な根拠を準備する
ガイドラインは味方になりますが、成功するかどうかは「根拠を数字で示せるか」にかかっています。
RE GENの視点
値上げ交渉は「強気に言えば通る」ものでもなく、「絶対に無理」でもありません。
重要なのは、ルールを理解し、数字で裏付けた説明を準備すること。
RE GENでは、公取委のルールを踏まえつつ、現場で通じる交渉設計や資料づくりをお手伝いしています。
まとめ
- 値上げ交渉は法律で「聞く場を持つ」ことが推奨されている
- メーカー側には「確認義務」と「証跡管理」が求められている
- サプライヤーは数字で裏付けた説明を行うことで通りやすくなる
👉 詳しくは公取委の「価格転嫁円滑化施策」ページも参考にしてください。
知っておくだけで、交渉の景色が変わりますよ。
内部リンク
- サプライヤー評価の基本項目とは?
- 在庫削減のコツ:分析の視点から考える
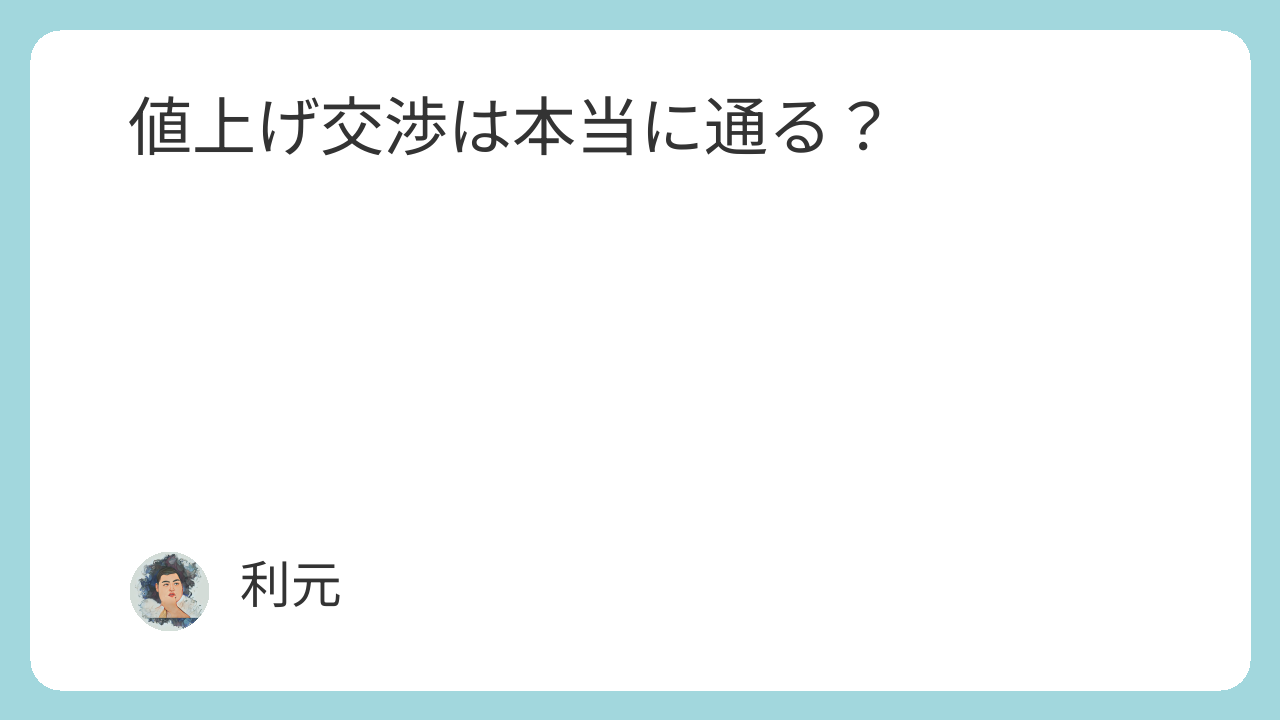
コメント