調達の仕事は「安く買うこと」ではありません。倒れないパートナーを選び、共に育てることです。
だから、見る数字は多くなくていい。必要なのは、前編で「会社の身体」の要だと紹介した3つの主要な数字に絞り込むことです。
1. 🥇 粗利率(売上総利益)──現場に“余裕”があるか
粗利は、その会社が本当に生み出している付加価値の源泉であり、現場の作業品質に直結します。粗利が低い現場には、共通して「余裕のなさ」が滲み出ています。
| 粗利が低い現場の兆候 | 粗利が高い現場の兆候 |
|---|---|
| 工具の刃が替えられていない、手入れが後回し | 動きにムダがない、作業が洗練されている |
| 片付けが「時間があれば」に回され、5Sが崩れがち | 声が荒れない、現場が静かで落ち着いている |
| 設備音が荒い、手戻りが多い | トラブル対応が速く、体系化されている |
これは能力ではなく、余裕の問題です。
粗利は、現場の文化と品質を維持するための「余白」です。
2. 🧱 自己資本比率──倒れにくさは“挑戦の余白”
自己資本比率は、会社を支える体幹です。借金(他人資本)に大きく依存し、自己資本が薄い会社の現場は、「攻め」ではなく「耐える」空気になります。
自己資本に余裕がないと、未来の収益を生む設備投資や人材育成といった「挑戦」に手が回らなくなります。
| 自己資本が薄い現場の空気 | 自己資本に余裕がある現場の空気 |
|---|---|
| 設備更新が止まる、古い設備に頼り続ける | 改善に積極的に投資できる、最新技術を導入 |
| 人材育成に手が回らない | 技術的な力を蓄えられる、若手が育つ |
| 改善提案が出ない、現状維持で精一杯 | 長期の視点で関係が作れる |
挑戦できる会社は、取引の未来を一緒に作れる会社なのです。
3. 🌬️ 現金・預金(流動性)──呼吸ができるか
「現金・預金」の残高や、短期的な支払い能力(流動性)は、会社の呼吸です。呼吸が浅い会社は、計画よりも突発的な“火消し”に追われます。
- 不具合対応で倒れる(余裕がないため、小さなトラブルで動けなくなる)
- 一時的な納期遅延が長期化する
- 「やれること」ではなく「今できること」で判断する
一方、現金の備えがある会社は、トラブル時にも立て直しが速く、判断がぶれません。
誠実さや迅速な対応は、財務に裏打ちされます。
4. 🔠 数字 → 現場 → 調達判断 の翻訳表
調達担当者が財務諸表と現場を往復することで、以下の判断に繋げることができます。
| 数字 | 現場での兆候(翻訳) | 調達が判断するべきこと |
|---|---|---|
| 粗利 | 作業の丁寧さ / 手戻りの少なさ | 品質の長期安定力と価格交渉の余地 |
| 自己資本比率 | 設備更新 / 改善提案の有無 | 共創可能性(未来を共に作れるか) |
| 現金・流動性 | 立て直しのスピード / 判断の安定性 | トラブル時の信頼維持能力とリスク |
調達は「値段を叩く人」ではありません。これらを“読み”、未来に向けた関係を設計する人なのです。
5. 👓 RE:GENの視点:財務は「人」と「現場」の翻訳
数字に強いだけでは足りません。現場に強い目がなければ、財務諸表はただの情報です。
財務は、「人」と「現場」の状況をバイヤーに伝える翻訳です。
調達とは、この翻訳された情報を活用して、自社とサプライヤーの双方に利益をもたらす関係を扱う仕事なのです。
✅ 後編まとめ:倒れない相手を選ぶことが、未来をつくる
- 粗利=現場の余裕(品質の安定)
- 自己資本比率=挑戦できる力(未来への投資力)
- 現金=呼吸(トラブル時の対応力)
- 調達は「叩く」ではなく「育てる」関係の設計者
倒れない相手を選ぶことが、結果的に自社の安定と、明るい未来をつくることにつながるのです。
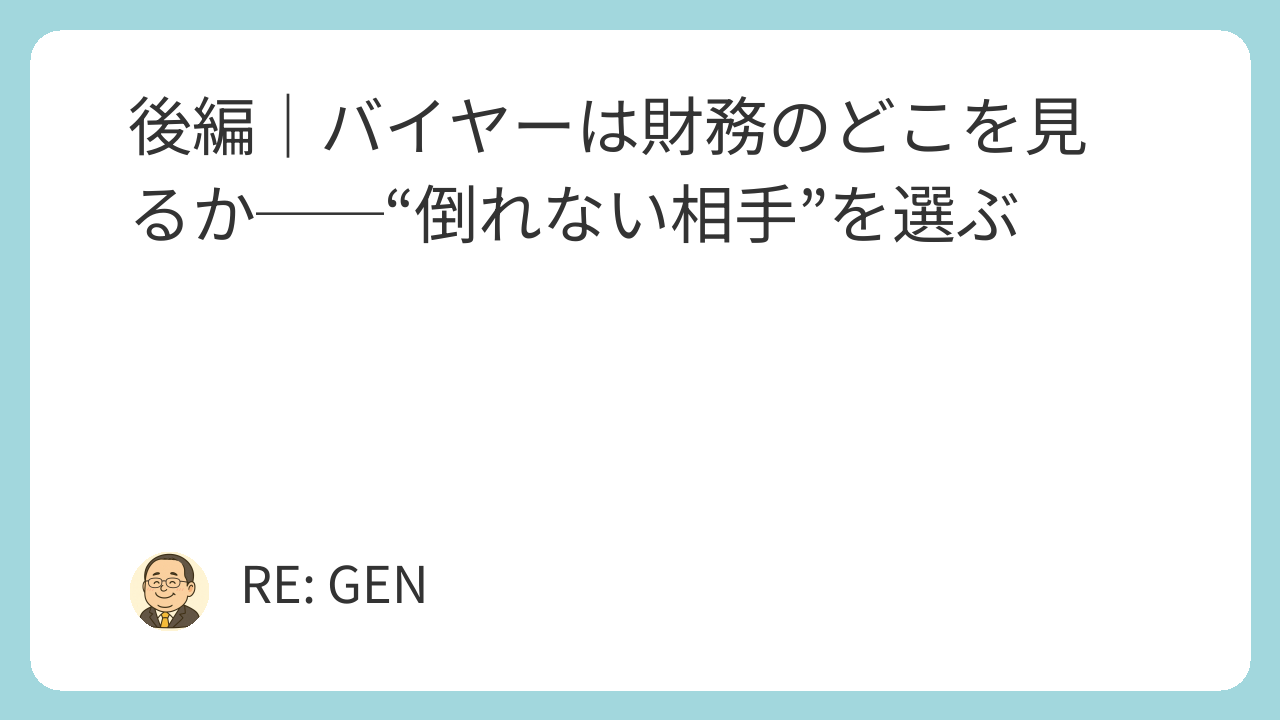
コメント