合理化は「率」より「額」!経営と現場のKPIの溝を埋める方法
「今年はコストを5%削減しろ!」
「いやいや、昨年100円の部品は今105円なんですけど…」
製造業の現場では、こんな会話が日常茶飯事です。
経営は「率」で合理化を語り、現場のバイヤーは「額」で苦しむ。この小さなKPIのズレが、やがて大きな溝を生むのです。
経営側の悲劇:「率」が招くKPIの歪み
経営者は、会社の健全性を判断するために「率」というわかりやすい指標に頼りがちです。
しかし、ここには大きな落とし穴があります。
- 売上の掛け算効果
売上が伸びれば、自動的に削減目標額も膨らみます。実際には新規案件や値上げ対応で手一杯でも、「前年比5%」が課され、現場は理不尽なプレッシャーにさらされます。 - 数字の魔力
逆に、売上が増えたおかげで削減率目標を達成することもあります。実態はほとんど合理化されていないのに、「目標達成」と報告され、経営は安心してしまう。これでは、本当に企業を強くする合理化にはつながりません。
現場側の悲劇:「額」が報われないKPIの罠
一方、現場のバイヤーは日々「額」と格闘しています。
- 評価のジレンマ
数千万円規模の高額部品を1%削減し、会社に大きな利益をもたらしても、小さな部品群の「率」が未達なら「評価されない」。 - 達成という名の虚無感
逆に、数万円しか削減できなくても、率だけ見れば「目標達成」。こうして、現場の本当の貢献が見えなくなり、モチベーションを奪っていきます。
RE:GENが提案する「額」を基点とした調達改革
RE:GENは、この不毛なギャップを埋めるために存在します。
- 戦略1:ABC分析で「額」を可視化
全購入品目を年間購入額順にABCランクで整理。どこに注力すれば最も大きな合理化「額」が出るかを明確化します。 - 戦略2:評価軸の再構築
「削減率」だけでなく、「削減総額」「提案件数」「仕組み化の進展度」といった軸を加え、バイヤーの貢献を正しく評価します。 - 戦略3:全社を巻き込む仕組み化
調達・開発・製造が一体となり、全社的に「額」で合理化を追求できる仕組みを構築します。
まとめ:経営と現場をつなぐ合理化の新しいものさし
経営は「率」を追い、現場は「額」と格闘する。
このズレを放置すれば、経営は実態を見誤り、現場はやる気を失います。
RE:GENは、「額」を基点に合理化を再定義し、経営の満足と現場のやりがいを両立させる調達改革を実現します。
「本当に削減できたのはいくらなのか?」
今こそ、その問いをKPIの中心に置くべき時です。
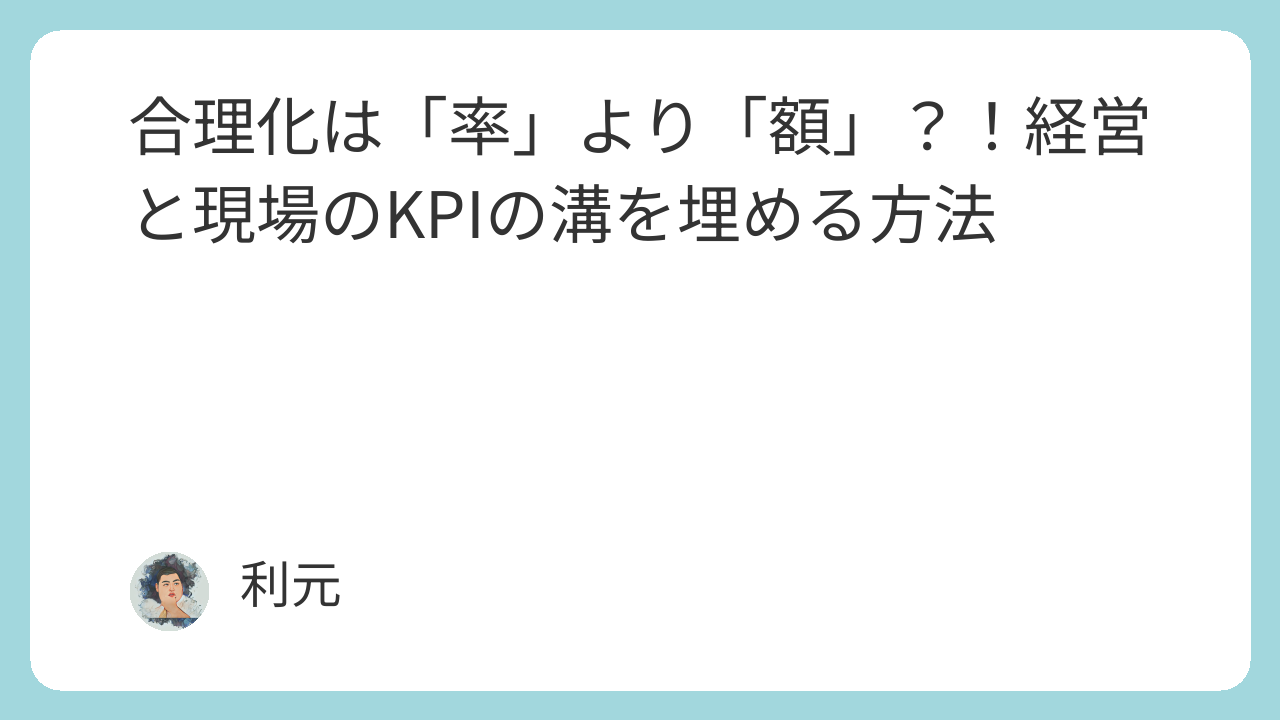
コメント