「同じ図面で、同じ加工なのに、見積額がA社は10万円、B社は40万円。なぜこんなに違うのか?」
これは、ものづくりバイヤーや経営者なら一度は経験する“あるある”です。品質や技術レベルが極端に違う会社でもないのに、なぜここまで差が生まれるのか。今回はその背景を整理し、調達担当が知っておくべき視点をお伝えします。
1. 価格差の第一の要因:設備・得意分野の違い
工場ごとに「得意・不得意」があります。最新のマシニングセンタを持つA社なら一発で削れるものを、古い設備しかないB社は段取り替えや外注が必要になる。結果、同じ図面でも工数や外注費の分だけ価格が跳ね上がります。
これは単なる「効率の差」ではなく、会社の戦略や投資の方向性によって必然的に生まれる差です。
2. 見積テーブルの曖昧さと営業方針
もう一つ大きいのが「見積テーブルの曖昧さ」。
ある会社では、原価を積み上げるよりも「社内で決めた掛け率」でざっくり価格を決めているケースがあります。さらに営業方針として、「試作品など単品加工は赤字リスクが高いから、あえて高く見積もる」ことも珍しくありません。
つまり、見積価格は必ずしも“実際にかかるコスト”を正確に反映しているわけではなく、“会社としてどう売りたいか”の姿勢が表れているのです。
3. 曲げられない事情がある
バイヤーから見れば「もっと安くしてほしい」と感じても、会社には曲げられない事情があります。
たとえば、あるメーカーは「単発の小ロットでは儲からないから、見積を高くして自然と受注を避ける」方針を持っている。別の会社では「利益率◯%以上でなければ承認が下りない」という社内ルールがある。
つまり、提示された価格は担当営業の一存では動かせない。背後には「会社の戦略」や「組織の縛り」があり、それが価格差の背景になっているのです。
4. 価格差あるあるの実例
- 試作部品での事例
A社:自社の得意分野、社長直轄でスピード対応 → 見積10万円。
B社:不得意分野、外注に回してリスクも上乗せ → 見積40万円。 - 量産品での事例
同じ図面でも、A社は「既存ラインに組み込めるから安くできる」。B社は「新規ライン立ち上げが必要」で人件費を積み増し。結果、価格差は数倍に。 - 海外調達の事例
現地工場は「人件費安」で低価格。国内メーカーは「保証体制込み」で高価格。どちらも“正しい見積”だが、前提が違う。
5. バイヤーが学ぶべき視点
価格差は単なる「高い・安い」の問題ではなく、
- 会社の設備・技術の得手不得手
- 営業方針や利益率ルール
- 見積テーブルの曖昧さ
- リスク見積もりの考え方
こうした要素の組み合わせで生まれるものです。
したがって、バイヤーがやるべきことは「価格の数字だけで判断しない」こと。見積の裏にある事情を聞き取り、比較し、納得できる理由を見つけることが重要です。
6. RE:GENからの提言
相見積もりの本当の価値は「安い会社を探すこと」ではありません。むしろ「なぜこんな差が出るのか」を理解することで、自社の調達戦略を賢く立てることにあります。
- 見積根拠を丁寧にヒアリングする
- 得意不得意を見極め、適材適所で依頼する
- 単発か量産か、戦略的に発注先を分ける
RE:GENは、大手メーカー調達の知見をもとに、サプライヤーの見積背景を読み解き、最適なアプローチをアドバイスします。価格だけに振り回されない「戦略的調達」を実現しましょう。
まとめ
「同じ図面で4倍の価格差」は決して不思議なことではありません。そこには会社ごとの設備、得意不得意、営業方針、組織の事情といった“見えない要因”が隠れています。
バイヤーに求められるのは「安い見積を拾う力」ではなく、「価格の裏側を読み解く力」。相見積もりを単なる数字の比較で終わらせず、学びと戦略に変えることこそが、調達の本質です。
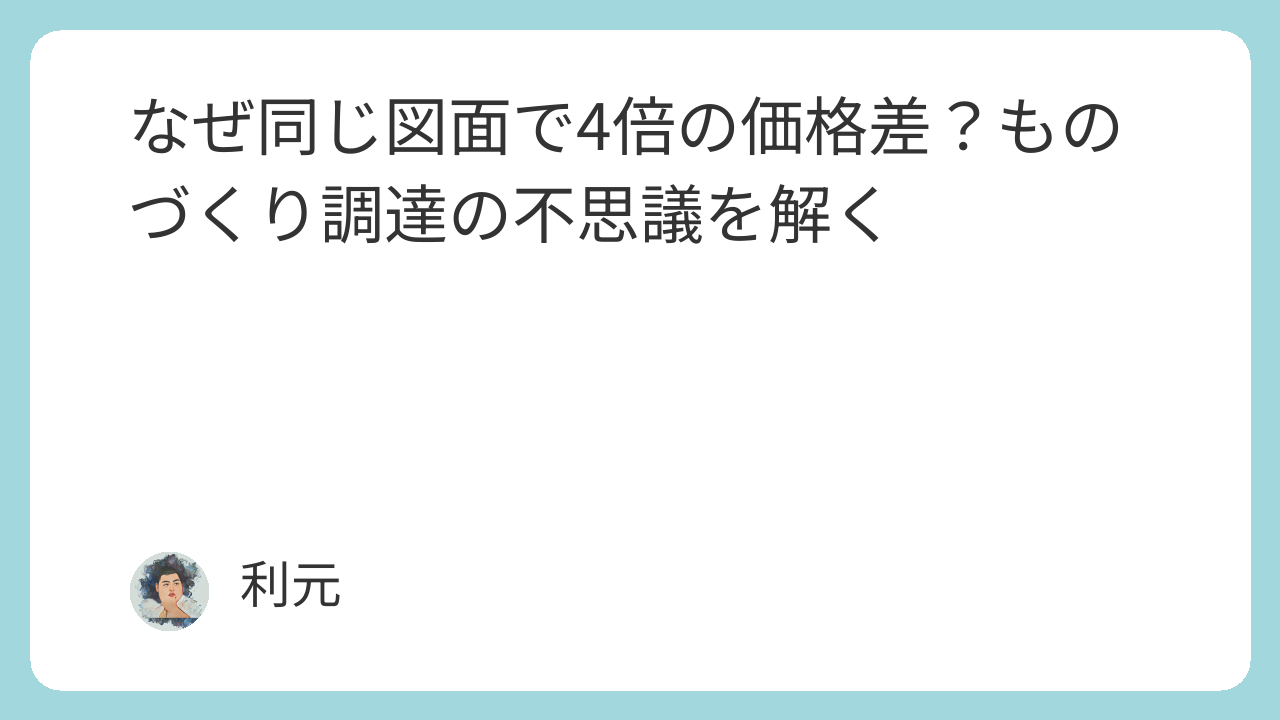
コメント