1. 導入:提示価格は本当に妥当なのか?
「この見積もり、高いのか安いのか分からない」
「もっと下げられるはずなのに、どう切り込めばいいのか…」
バイヤーにとって、サプライヤーから提示される価格の妥当性を判断することは常につきまとう課題です。数字だけを見ても、それが適正かどうかは分かりません。
そこで必要になるのが**「理論原価」**という視点です。これはバイヤーにとって、価格交渉を単なる駆け引きから「根拠ある戦略」へと変える切り札となります。
2. 理論原価とは何か?なぜ必要なのか?
理論原価とは、**ある製品や部品を、もっとも効率的かつ合理的に製造した場合に発生する“あるべき姿の原価”**です。
たとえばサプライヤーの提示価格が10,000円だったとして、理論原価を試算したら7,500円と見積もれたとしましょう。この差は単なる「ぼったくり」ではなく、営業方針や工場効率、ロットの大きさ、歩留まりの違いから生じているかもしれません。
バイヤーが理論原価を意識することには、次の3つのメリットがあります。
- 適正価格の物差しを持てる
「この価格は本当に妥当か?」を判断する基準になります。 - 交渉力が増す
単なる「もっと安くしてほしい」ではなく、根拠をもとに具体的な交渉が可能になります。 - コストダウンの方向性が見える
「どの工程で無駄が多いのか」「どの条件を変えれば下げられるのか」が浮き彫りになります。
3. 理論原価の基本構成要素
理論原価を正確に出すのは難しいですが、骨子を理解するだけで交渉の質は大きく変わります。
① 材料費
- 使用材料の種類と量、市場価格、歩留まり。
- サプライヤーの仕入れ力やルートによって差が出やすい。
② 加工費(労務費+経費)
- 標準作業時間 × チャージレート(1時間あたりの加工コスト)。
- 設備の償却、電力費、オペレーター人件費などを含む。
- 段取り時間やロット効果も大きな変数。
③ 間接費・管理費
- 品質保証、検査費、運搬費、間接部門の人件費など。
④ 利益
- 一定の利益率は当然必要。過剰かどうかを見極める。
例:材料費3,000円 + 加工費3,500円 + 間接費500円 + 利益20% → 理論原価は約9,000円。
提示価格が12,000円なら、「なぜ3,000円の差があるのか?」と具体的に質問できます。
4. サプライヤーも「見えない敵」を意識している
サプライヤー側も当然、自社の理論原価を算出しています。
- この製品を作るには最低どのくらいかかるのか。
- どの条件なら利益を確保できるのか。
彼らも「理論原価」という見えない敵と戦いながら見積を組み立てています。
だからこそ、バイヤーが理論原価を意識することで、サプライヤーと同じ土俵で話ができるようになるのです。
5. 理論原価をどう活用するか?
理論原価は「一方的な値下げ要求」に使うべきではありません。建設的な活用方法は次の通りです。
- 質問の根拠にする
「この工程は標準時間で何分想定ですか?」
「材料の歩留まりはどのくらいですか?」
こうした質問は単なる値引き交渉ではなく、相手に改善の視点を促します。 - 代替案を一緒に考える
「この治具を共用化すればコストを抑えられるのでは?」
「ロットをまとめれば加工費を下げられるのでは?」
協働の姿勢が、信頼関係を強めます。 - 内部目標の設定に使う
自社として「この製品は理論原価ベースで〇円以下に抑えたい」と社内共有すれば、購買活動がより戦略的になります。
6. まとめ:理論原価はバイヤーの「盾」と「矛」
理論原価を知ることは、価格の裏にある仕組みを理解することです。
- 妥当性を見極める盾
- 具体的に切り込む矛
この両面を持つことで、交渉は「駆け引き」から「共創」へと変わります。
数字の裏にある現場や工程に目を向け、「なぜこの価格になるのか」を深く理解すること。それこそが、RE:GENが考えるバイヤーの成長であり、健全な調達の第一歩なのです。
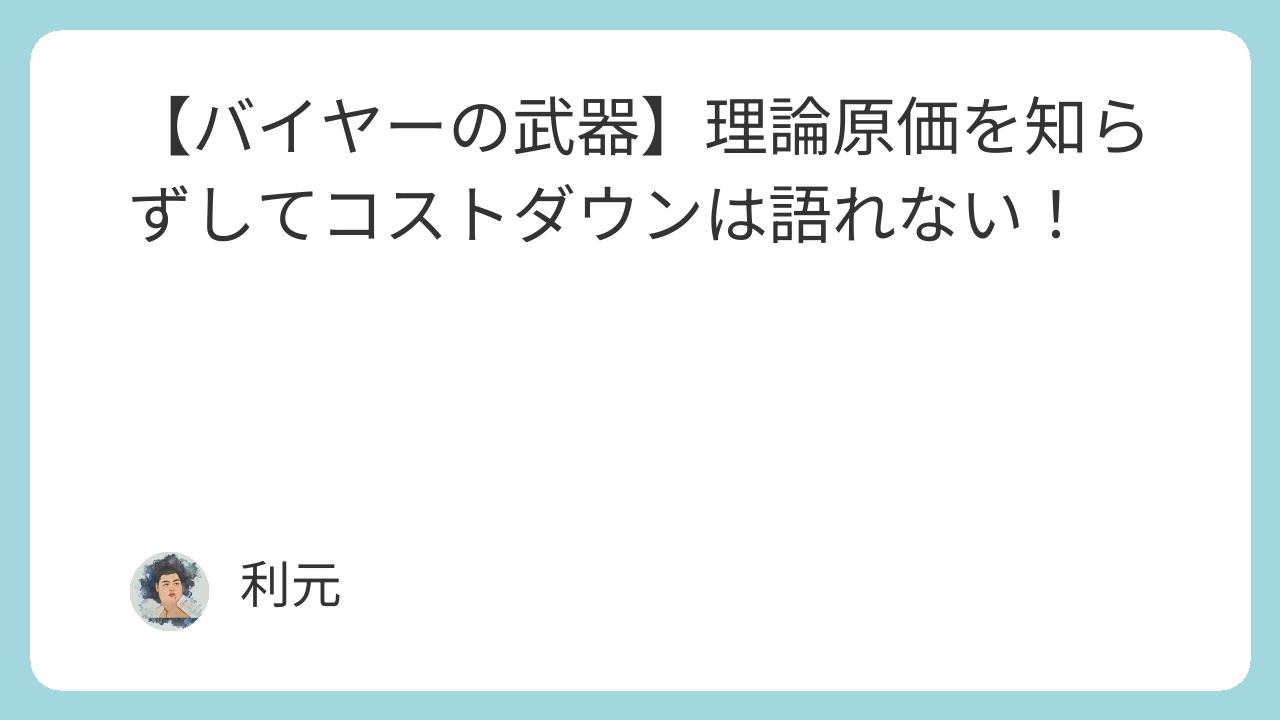
コメント