「調達は言われたことを伝えるだけ」「他部門に比べて地位が低い」――。
そんな声を聞くことは少なくありません。実際、毎日が発注や見積もり対応の繰り返しで、評価につながる成果が見えにくいと感じる人もいるでしょう。
でも、それは調達本来の姿でしょうか?
RE:GENは、この“常識”を見直す時が来ていると考えます。
調達の地位が低いと見られがちな理由
- 定型業務が多いから
発注やシステム入力は自動化できるのでは?と思われがち。 - 成果が目に見えにくいから
売上のように数字で表れず、地味に見られてしまう。 - 専門知識で不利に見えるから
設計や製造の専門的な話になると会話が難しく、調達が弱く見えてしまう。 - 「お願いばっかり」に映ってしまうから
値下げ交渉も根拠がなければ「お願いしているだけ」に聞こえてしまう。
こうした要素が積み重なり、調達は「地位が低い」というイメージを持たれてしまうのです。
RE:GENの視点①:調達は“翻訳者”
調達の役割を一言で表すなら、「翻訳者」。
設計や製造の言葉を、サプライヤーに伝わる形に翻訳する。
経営が求める数値やリスクを、現場で実現できるアクションに翻訳する。
異なる立場の“言葉”を行き来できるのは調達だけです。
つまり調達は、社内外をつなぐハブの存在なのです。
RE:GENの視点②:付加価値は「理論」と「共創」
お願いベースではなく、根拠のある提案と共創こそが調達の付加価値です。
- 理論原価を理解する
「この工程ならこのくらいが適正」と判断できれば、無理なく納得感のあるコストダウンができる。 - 在庫を設計する
単に減らすのではなく、流動・戦略・死蔵を見極め、持つべき在庫を持つ。 - 共創する調達
サプライヤーを“値切る相手”ではなく、“共に利益を作るパートナー”として関係を築く。
これらを実践できれば、調達は単なるコストカット部隊ではなく、利益をつくる戦略部門に変わります。
RE:GENの視点③:中小企業こそチャンス
大手は仕組みやシステムで管理できますが、中小企業では調達の判断が会社を大きく左右します。
- 経営者や経理と直結しているからこそ、調達の声が経営に届きやすい
- サプライヤー数が限られるからこそ、パートナーシップが深まりやすい
- 一つの判断が利益や信用に直結しやすい
つまり中小企業にこそ、調達が地位を上げられる土壌があるのです。
結論:「お願い調達」から「共創調達」へ
調達の仕事は、伝書鳩でもお願い屋でもありません。
翻訳者として社内外をつなぎ、理論と共創で会社の利益を支える存在です。
RE:GENは、そんな調達がもっと胸を張れる未来をつくりたいと考えています。
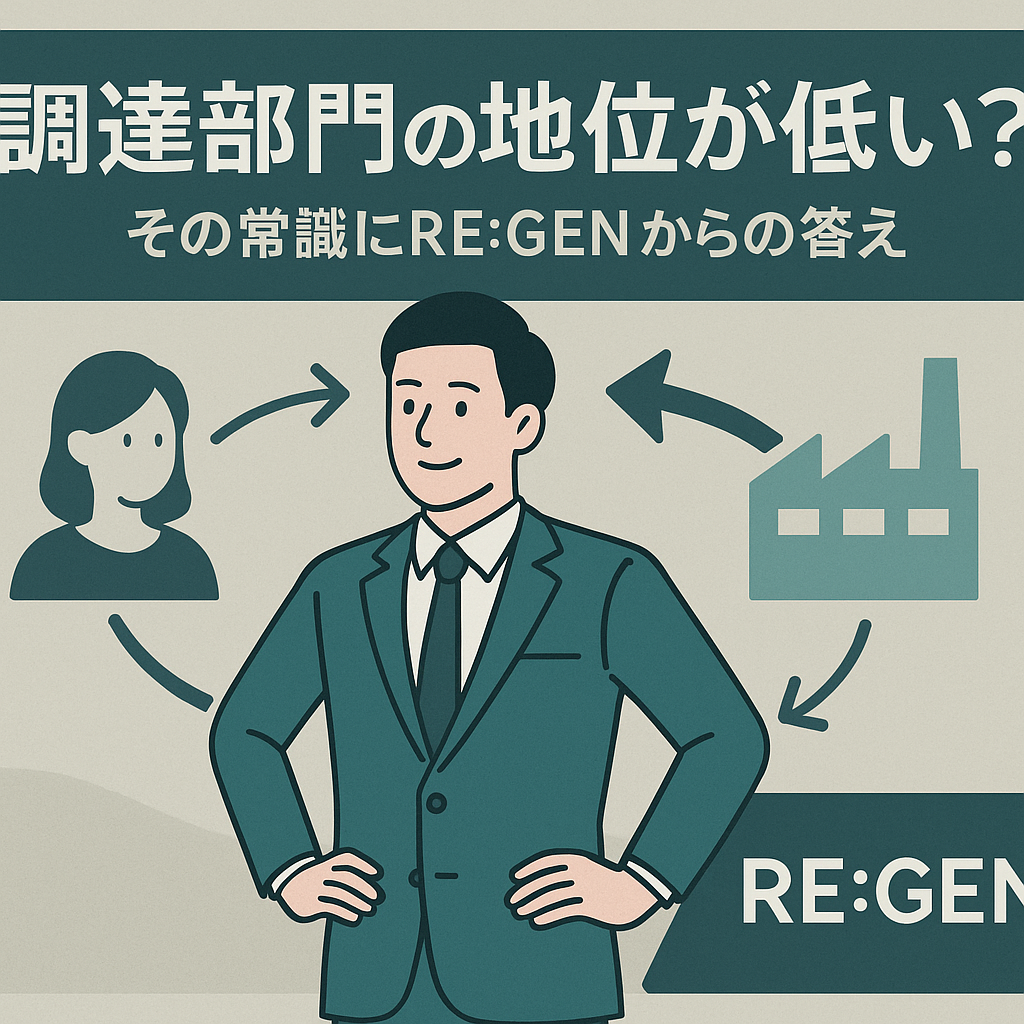
コメント