【豆知識】値上げ交渉と公取委のルール
~知っておくと得する調達の常識~
最近「値上げ交渉」がニュースでも話題になっていますね。
「でも実際はそんなに簡単に通るの?」と思ったことはありませんか?
実はここには 公正取引委員会(公取委)のルール が関係しているんです。
今回はそのポイントを、調達の現場感も交えてわかりやすくご紹介します。
1. なぜ公取委が関わるのか
中小企業が仕入先として大手メーカーに部品やサービスを供給する構図は、日本の産業でよくあるケースです。
ただ「原材料費が上がったから価格を上げたい」と思っても、買い手が強すぎると交渉すらできません。
そこで公取委は、「正当な理由があれば価格を上げても良い」 というガイドラインを出して、健全な取引を守ろうとしているのです。
2. ガイドラインの中身
公取委の「価格転嫁円滑化ガイドライン」にはこんなことが書かれています。
- 原材料費や人件費の高騰は正当な理由になる
- 買い手が一律に値上げを拒否するのはNG
- 「買いたたき」と見なされると独禁法・下請法違反になる可能性あり
つまり、サプライヤーの声を「聞かない」という態度は、法律的にもアウトになるのです。
3. 実はメーカー側に「確認義務」がある
ここは意外に知られていないポイントです。
公取委の方針では、メーカー側から「最近コストは上がっていませんか? 値上げは必要ありませんか?」と仕入先に確認することが推奨 されています。
そして、そのやりとりを「記録・証跡として残すこと」まで求められています。
これを知ると「えっ、そんなことまでしてるの?」と驚く方も多いでしょう。
つまり、値上げ交渉は「お願い」ではなく、仕組みとして義務づけられている部分があるのです。
4. バイヤー目線からすると
調達の経験から言うと、バイヤーも「全部断る」はリスクです。
「聞く耳を持たない」だけで法令違反と見なされかねません。
だからこそ、最近は 証跡を残すために「一度は値上げ要望を聞く」 という動きも出てきています。
逆に言えば、供給側はその機会を逃さず「具体的な根拠を提示すること」が大切になります。
5. サプライヤー側が気を付けたいこと
- 「一律で5%アップ」では説得力が弱い
- 原材料費や物流費などの内訳を整理して提示する
- 数字やグラフなど客観的な根拠があると通りやすい
ガイドラインは味方になりますが、結局は「数字で説明できるか」が成否を分けます。
6. RE GENの視点
値上げ交渉は「強気に言えば通る」ものでもなく、「絶対無理」でもありません。
ルールを理解した上で、根拠の整理と対話の準備 が欠かせません。
RE GENでは、公取委のルールに沿いつつ、現場で通じる交渉設計や資料づくりをお手伝いしています。
まとめ
- 値上げ交渉は法律で「聞く場を持つ」ことが推奨されている
- メーカー側から「値上げはありませんか?」と確認し、証跡を残すことも重要
- サプライヤーは、そのチャンスに数字で裏付けた説明を行うことがカギ
👉 詳しくは公取委の「価格転嫁円滑化施策」ページもチェックしてみてください。
知っておくだけで、交渉の景色が変わりますよ。
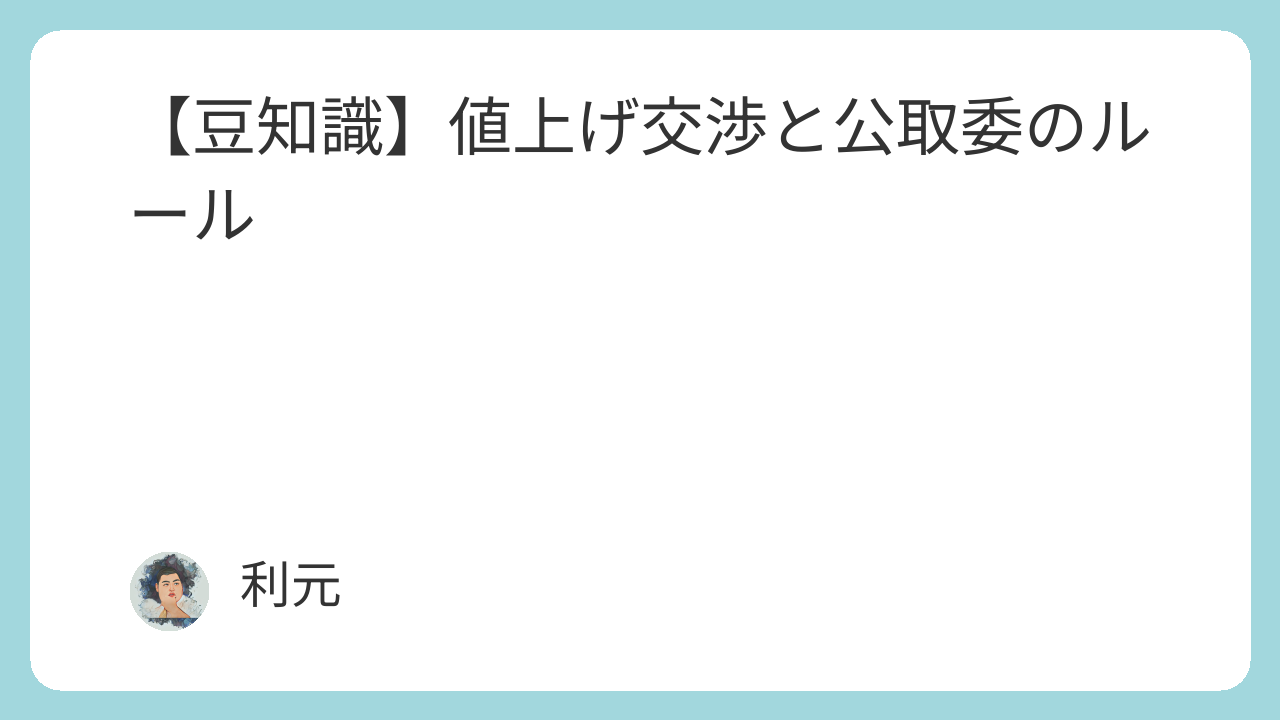
コメント